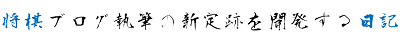詰将棋の世界第6回は無駄合いかどうかが微妙なケースの話
【当サイトの記事はPRを含む場合があります。】
「詰将棋の世界」の第6回、数学セミナー誌の9月号に掲載された回についての記事を書きます。
この回のテーマは、「無駄合い」でした。
無駄合いは2回にわたって解説されたのですが、第6回はその前半にあたります。
詰将棋の世界第5回出題分の解説について
それでは、さっそく見ていきましょう。
まずは第5回の解説がどんな感じだったかについてです。
いつもの通り、実際の問題は数セミでご覧になっていただければ幸いです^^
詰将棋の手筋が登場の第5回の第1問の正解手順
龍で王手するとき、龍を相手玉のいる段か筋に移動しますね。
そういう王手のしかたは、龍は斜めにも動けるので、通常は3通りあります。
どこに移動するかですが、普通の感覚だと、龍をなるべく玉に近づけようとしますよね。
「玉は包むように寄せよ」という格言もありますし。
でも、ときには、それでは詰まなくなってしまうケースもあります。
「そんなまさか」と思われるかもしれませんが、第5回の第1問はその例になっています。
どこに動かしても龍がとられてしまう状況の中で、龍を玉から話す手だけが、玉を詰ますことができる、というのがポイントです。
このような、龍が玉から遠ざかる王手は「ソッポ龍」と呼ばれ、よく見られる詰将棋の手筋なのだそうです。
「詰将棋の手筋」というのを私は知らなかったので、新鮮な響きがありました。
読者の皆さまは知っていましたか?
短編詰将棋ならではの「不利感」がよく出ている第2問
第5回の第2問は5手詰め。
中々難しい問題でした。
普通に駒を打っていったのでは玉を逃がしてしまいます。
相手の歩の上に金を動かしたり、相手のと金が効いているところに金を打って捨てたり。
最初の金を動かす手にしても、玉の逃げ道をつくってしまう手だったりで実戦だったら指しにくい手ばかりです。
このような、心理的な指しにくさを「不利感」というそうです。
この「不利感」は短編詰将棋でよくテーマにされるそうです。
短編作品は手数が短いからすべての王手を調べれば正解に行きついてしまいます。
だからきっと、作品の難しさを確保するためには、本手順が意外な手である必要があるわけですね。
第5回の第2問の難しさは正解手順の意外性にあり、うっかりすると全く的外れな手を読んでしまいそうになります。
詰将棋における「無駄合い」って?
「合駒」というのは、以前にもどこかで説明しましたね。
簡単に言うと、飛車などの「飛び道具」的な駒で王手をかけられたときに、王との間に持ち駒を打つことです。
飛び道具の「効き」を、自分の駒で遮断するわけです。
「無駄合い」とは、まったくの無駄になってしまう合駒のことです。
初心者時代によくやった将棋の「悪あがき」の一つ
合駒が「無駄」になるということを、一応説明しておきましょう。
初心者時代に、上級者の方たちは投了するのがかなりはやいと感じたことはないでしょうか?
強い人は、自分の負けが決定的であることを見きるのがはやいです。
特に、自玉に詰みがある場合は、初心者にはまだ読み切れないくらいの場面で投了します。
逆に、初心者は、最後の最後まで指そうとすることが多いのではないでしょうか?
自分に持ち駒があれば、最後の1枚まで使おうとします。
相手の王を詰ませるわけがないと分かっていても、王手がかかるうちはかけようとしたりしましたよね^^
将棋ソフトなども、そういう傾向が結構あったりしますね。
ソフトの場合、不利になると、もっと粘ろうとせずに急に無駄な王手を連発してきます。
これは弱いソフトだけでなく、アマ三段くらいのレベルに設定してもそういうことがあります。
ソフトの話はともかく、無駄な合駒というのも、そういう悪あがきに近いものだと思えばイメージしやすいでしょう。
本手順では無駄合いは打たない
詰将棋で玉方が無駄合いを打った場合、手数が長くなって持ち駒余りが生じてしまいます。
もしも無駄合いを認めてしまえば、とどめに飛び道具で王手する限り持ち駒が余ってしまいます。
実際には、無駄合いは玉方の王手として認められていないので、とどめに飛車や香車などの飛び道具が使われる詰将棋はたくさんあります。
要するに、詰将棋の正解手順、本手順においては無駄合いは出てきません。
「無駄」かどうかが判断しにくい合駒
実は、無駄合いというのは、色々なパターンがあり、「無駄」と断定していいかどうかが難しいものもあります。
第6回では、その難しさが分かるような具体的な問題を取り上げて説明してくれています。
無駄合いかどうか迷う合駒って?
無駄かどうか、ちょっと判断に迷うな、と感じる合い駒とはどのようなものでしょうか?
パターンが互いに異なる具体例が2つ紹介されていました。
一つは目、確かに「無駄」な感じはしますが、少し読みを入れないと分からないタイプでした。
玉方が合い駒をした後に、攻め方がそれを取り返す手が、別の飛び道具による空き王手になっていて、それに対しての合駒が無効になっている、というタイプでした。
初心者時代のただの「悪あがき」と違って、一目で明らかに無意味な合駒ではなく、少し考えた結果、「無駄と言えば無駄かな」、となる、みたいな。
二つ目は、もっと判断に迷うかもしれません。
合駒を打つ手は、駒余りになるし詰みを防げていません。
しかし、その合駒を打つと打たないとで、詰め上がりの形が変わってしまうのです。
第5回取り上げられた例では、龍の位置が変わってしまっています。
改めて思いますが、詰将棋というのは、実に色々な要素があるのですね。
無駄合いは詰将棋マニアの間でも意見がわかれる
さて、無駄合いかどうかについては、一致した見解は得られているのでしょうか?
実は、詰将棋マニアの間でも、意見がわかれるのだそうです。
「無駄」の厳密な定義がなく、決定版となる判断基準が現状存在しないとのことでした。
しかも、「無駄合いがどうかが微妙なケース」は、紹介されたもの以外にも色々なケースがあるそうです。
そして、微妙なものについては、雑誌などには出題しないようにしているみたいです。
詰将棋のルールは時代の流れとともにどんどん明確化されてきたわけですが、それでもはっきりと決めきれない部分があるのですね。
まとめ
いかがでしたか?
詰将棋の「無駄合い」について書かれた数セミ連載「詰将棋の世界」第6回についてまとめました。
ところで、将棋ではすでに、コンピュータの占める位置が大きくなってきていますね。
しかし、詰将棋の分野に曖昧な要素が存在することは、詰将棋や将棋はやはり人間のものであると感じさせてくれる気がします。