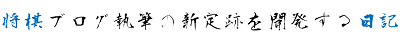詰将棋選手権の本がある!どんなことが書いてあるの?入手方法も
【当サイトの記事はPRを含む場合があります。】
2018年4月7日(土)は、詰将棋解答選手権の初級戦と一般戦の日でした。
読者の皆さまは参加されましたか?
このブログでは、2017年の詰将棋選手権の前に記事を書きましたが、その後ほとんど選手権について触れずにきましたね。
詳しい方はご存じかもしれませんが、詰将棋選手権は毎年、大会についての本を出しています。
実は、詰将棋解答選手権2017の冊子を手に入れたので、ずっと記事にしようと思っていました。
そして、記事を書かないうちに、いつの間にかもう2018年の初級戦・一般戦まで終わってしまいました(汗)。
というわけで(?)、今回のテーマは、詰将棋選手権大会の本についてです。
目次(もくじ)
詰将棋解答選手権の本って?
まずは、さきほどから話にでてきている、「詰将棋選手権の本」とか「冊子」とはそもそも何のことかを説明しますね。
毎年、詰将棋選手権の大会の何ヶ月か後に出版される小さめの本があって、大会についての報告がまとめられています。
本の書名は例えば、「詰将棋解答選手権2017」のような感じになっています。
このブログでは、大会そのものと区別するために、「の本」とか「の冊子」をつけて呼ぶことにしています。
なんとなくイメージがつかめてきましたかね。
では、本にはどのようなことが書かれているのでしょうか?
以下では、私がもっている2017年の本を参考にして説明しますね。
おそらく例年同じような感じだと思いますので、多少は参考になるかと思います。
チャンピオン戦と初級・一般戦の問題や解説を掲載
大会で出題された問題とその解答・解説が読めます。
詰将棋選手権大会は、チャンピオン戦と初級戦・一般戦というレベル分けがあります。
各レベルで出題された問題について、解答・解説が読めます。
さらに、採点基準(配点)や正答者数に平均点、講評なども書かれています。
詰将棋解答選手権大会の本を手に入れる方法1(将棋会館)
詰将棋選手権の本はどうやって手に入れるのでしょうか?
藤井六段4連覇で話題になった2018年の選手権の本がでたら、是非欲しいですよね。
私自身が、「詰将棋選手権2017」を入手した方法ですが、千駄ヶ谷の将棋会館1階にある売店で買いました。
確か、2017年秋か冬の、週末のお昼頃に行ったと思うのですが、かなり混雑していて驚きましたね(笑)。
おそらくは藤井四段(当時)のグッズを買うお客さんで、将棋会館の売店は大変賑わっていました。
2階の道場もかなり人が多かったです。
そして、藤井グッズを大勢の人が買う中で、目立たないところにある詰将棋選手権の本を選んで買う私。
思わず我ながら通だな、と自画自賛してみたくなりました(笑)。
混雑や交通費が特に問題にならない人であれば、このように、将棋会館の売店で買うこともできます。
(ただし念のため事前に問い合わせを入れて売りきれていないかを確認した方がいいかも?)
選手権のブログによると、東京だけでなく、関西の将棋会館でも売っているようです。
詰将棋解答選手権大会の本を手に入れる方法2(郵便振替)
詰将棋選手権の本を購入する方法ですが、将棋会館に足を運ばなくても済む方法もあります。
参考サイト(外部リンク): 「詰将棋解答選手権2017」が発売されました。
「クリックポスト」という、簡単に荷物を送れる郵便サービスを使って送られてきます。
肝心の注文方法ですが、上記リンク先に記載の振り込み先に郵便振替を行います。
商品自体の値段に加え、送料もかかりますが、多くの人にとっては、将棋会館まで行く交通費に比べれば安いでしょうね。
なお、上記リンク先には、「詰将棋パラダイスでも扱っている」との記述がありますが、こちらについては詳細はよくわかりませんでした。
それからもう一つ、「将棋情報局」で購入することもできるようです。
ただ、2015、2016、2017年の「詰将棋選手権」の本については、「将棋情報局」ではすでに在庫なしとなっているので、もしかしたらもうどこでも手に入らないのかもしれません(汗)。
ただ、若島さんが優勝された2014年の本については、(記事執筆時点で)「在庫あり」との表示になっていました(こちらも在庫は「残り5」と少ないですが)。
ともあれ、2018年の大会の本が出版された際には、きっとまた同様な方法で販売されると思うので、今のうちに是非購入方法をおさえておいてくださいね^^
大会当日の写真もたくさん掲載されている
「過去問なら選手権大会のブログからみられるし、わざわざ本を買わなくてもいいかな。。。」
そう思った方もおられるかもしれませんね。
確かに、実際の参加者の正答率などがわかるのは貴重ではありますが、大会参加に興味のない人にとってはさほど魅力的でないかもしれません。
でも実は、選手権の本をおすすめしたい理由は、他にもあります^^
一番の理由は、写真が豊富に掲載されていることです。
チャンピオン戦当日の棋士や奨励会員、女流棋士の写真が載っていますので、将棋ファンには是非おすすめしたいです。
写真は残念ながらほとんどが白黒ですが、表紙とその裏面(?)のはカラー写真です。
2017年版では、藤井四段(当時)が表紙ですが、裏側の写真にも藤井四段(当時)が、広瀬八段や行方八段とともに写っています。
プロの対局のときの緊張した感じと違って、リラックスした雰囲気が伝わってくるのが嬉しいですね。
また、各地域の初級戦・一般戦の参加者の写真もあります。
指す将棋ファンの場合は、道場や大会などでみかける人の写真があったりするかも(?)
開催レポートもあるので、選手権の雰囲気だけでも味わえて楽しいと思いますよ^^
まだ将棋の道場や教室、大会に行ったことのない方にも、将棋好きが集まったときの空気感がわかっていいかも(?)
さらに深く詰将棋解答選手権に興味ある人へ
上に書いたことからおわかりのように、詰将棋選手権の本は、詰将棋や将棋、棋士が好きな人にとって楽しめる本です。
ここからはより色々な楽しみ方をしたい人やアクティブな人向けの情報も書きますね。
参加人数の変化や開催地の増加がわかる
将棋に興味をもつ人が増えていくことが嬉しい、新しいことにチャレンジしていく人の姿をみたり想像するのが好きだ、という人向けの楽しみ方です。
詰将棋選手権の本の最初の方には、大会全体の参加者の数や、開催された会場のリストが載っています。
ひょっとするとこれらの情報は、選手権のサイトでも読めるものもあるかもしれません。
ですが、紙の本にコンパクトにまとまっているのは便利です。
参加人数については前年比較もあるので、将棋ファンが全国に増えてきていることがわかる気がして、喜ばしいものがありました。
特に、2018年度はチャンピオン戦、初級・一般戦ともに会場が増えたので、2018年の本が出たらまた2017年度と比較して楽しみたいと思っています^^
初級・一般戦は、参考までに、全国の会場の中で上位の成績をおさめた方のリストが得点や解答時間とともに出ているので、これもとても参考になります。
大会主催者になれる?新規開催地募集の案内
将棋ファンの中には、本当に熱心な人がいて、関心させられます。
アマチュアながら将棋の普及活動的なことをされている方の存在を知ると、頭が下がります。
私と一応知り合いの方で、将棋の普及に熱心なある方も選手権に参加されたみたいですので、そういう方も参加者には結構いるのかもしれません。
そういう熱心でアクティブな方に朗報(?)です。
なんと詰将棋選手権は、開催地を公募しています。
地域エントリー料3000円がかかりますが、特典として書籍がもらえるそうです。
さらに、写真付きの開催レポートを選手権の本に載せてもらえます。
イベント運営が好きな方たちには、きっと楽しいと思います。
ただし開催レポートの中には大会運営スタッフでない一般の方が書かれたものもあるようですが。
初級戦のみ、一般戦のみの開催でもOKとのことですので、負担にならないように短時間の開催も可能です。
普段グループで将棋活動をされてる方や仲のいい熱心な将棋仲間がたくさんいる方は、スタッフを集めて初級・一般戦を主催してみてはいかがでしょうか?
開催に興味あるグループの代表者の方は、詰将棋選手権の本に記載の連絡先までお問い合わされてみてください^^
もちろん、例年主催しているグループに入れてもらうという手もありますね。
出題者になれるチャンス?詰将棋の新作問題募集
主催者だけでなく、詰将棋の問題の作成者として大会に関わるチャンスもあります。
誰にもみせたことのない問題であれば、応募できます。
しかも採用者には、選手権の本がプレゼントされます!これは嬉しいチャンス!
でも、、、詰将棋のオリジナルな問題をつくるなんて難しい。。。
そう思う方が多くても当然です。
しかし、募集されている手数は1手詰めから39手詰めまで、幅広いです。
ごく短い手数の問題であれば、つくることができるかもしれません。
積極的にチャレンジする精神でいくと、いい経験になるかもしれませんので、頭の片隅に置いておくといいでしょう^-^
まとめ
いかがでしたか?
今回は毎年出版される詰将棋選手権の本の魅力や楽しみ方について書いてみました。
アクティブな方向けに書いた部分は、結構無責任に書き過ぎましたかね(汗)。
2017年版は7月ごろに発売されたようですので、2018年版の発売まで3ヶ月ほどになりますね(記事執筆時点で)。
楽しみにしておきましょう^^