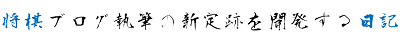将棋における反則、「禁じ手」について
【当サイトの記事はPRを含む場合があります。】
前回は、将棋道場のことを少し書きました。
今回はまた、将棋自体の基本事項について書きます。今度は、「禁じ手」についてです。
将棋における禁じ手
どいうわけで、将棋の反則についてです。反則は、禁じ手ともいいます(多分)。
将棋の基本ルールの確認として、反則の例を書いていきますね。
まだルールを覚えていない方は、是非ご参考下さい^^
待った
これは有名ですし、前に書きましたのでみなさんよくご存知でしょうね。
将棋では一度指した手を変更する行為「待った」はできません。
ただし、正式な勝負の場でなければ、待ったをありにして指すことはありな場合もあっていいと思います。
中の良い人たち同士で楽しみながら対局するときなどは、一気に勝負が決まってしまうような手が指されたら、それ以上続けても楽しくないことがありますので。
そういうときに、面白い将棋を続けたいので待ったを許すようにするのもありでしょう。
ただしこれは必ず双方の合意の下にやるようにして下さい。
また、待ったをすることが習慣になってしまうと中々上達できませんので、ミスをして一気に形勢が決まってしまったとしても、その場で投了するかいったん最後まで将棋を終えてから感想戦という形で改めて元の局面から勝負を再開するのがベストな方法だと思います。
そのような感想戦の際は、まわりの観戦者の方には口出しをしないようにお願いしておくといいかもしれませんね。
「改めてこの局面から勝負しなおしたいので、どう指せば良いかが分かっても黙っていてください」という感じでお願いすれば、きっと理解してもらえます。
二手指し

これも簡単ですね。
将棋は交互に一手ずつ指していくものでしたね。
ですので、自分ばかり二手連続して指す、「ニ手指し」は反則になります。
ただ、以現在の手番がわからなくなってしまうこともあるんですよね・・・。
前にも書いたように、どちらの番なのかわからなくなってしまったときは、相手に確認するといいでしょう。
二歩
将棋盤の縦の列のことを筋、横の列のことを段と呼びます。
前にも書きましたように二歩とは、すでに自分の歩がある筋に、持ち駒の歩を打ってしまうことです。
これが何故反則と定められているかを理解するのは、将棋に入門したばかりの時点では分からないかもしれません。
歩という駒の使い方が分かるようになると、もしも二歩を認めてしまえば、二歩がかなり強力な手になってしまうことが分かります。
歩はあくまでも一番弱い駒であって欲しいので、将棋では二歩はなしになっている、というわけでしょうね^^
打ち歩詰め
打ち歩詰めを禁じ手にする理由も、二歩と同じような理由があるように感じます。
打ち歩詰めとは、持ち駒の歩を打って相手の王将を詰ますことです。
反則ですので、もしも打ち歩詰めをやってしまったら、負けになります。
打ち歩詰めなんて滅多になさそうな気もしますが・・・。
意外と実戦でも打ち歩詰めの筋が水面下にあったりします。
また、詰将棋の問題では、打ち歩詰めさえ認めれば簡単に詰むのに、というようなものがわりとよくあるものです。
打ち歩詰めを避けて詰ますために、かなりの工夫が必要になったりします。
そういう意味では、打ち歩詰めはかなり強力な手であるともいえそうです。。
二歩同様、そうした強力な手段は反則扱いして制限した方が良いので、反則扱いになっている、というわけですかね。
またもう一つの理由として、「歩の分際で王将を詰ますとは何事か」というものがあるという話を聞いたことがあるように思います。
やはり、歩はあくまでも弱い駒であって欲しいのでしょうね。
もっとも、打ち歩詰めではなく、「突き歩詰め」なら反則ではないので、この二番目の理由はあまり説得力がないかもしれませんね。
その他の禁じ手
上記以外の将棋の反則の多くは、それ程難しくありません。
一番当たり前の反則は、駒の動きを間違えて、本来なら行けないところに動かしてしまうことですね。
それ以外だと、例えば持ち駒を打つときに、裏返して打ってはいけません。
打ったばかりなのにいきなり成り駒になっていてはいけないわけです。
その他に、例えば敵陣の5段目から4段目に銀を動かしたのに、銀を成り銀にしてしまうなど、本来なら成れないのに成ってしまうことも禁じ手です。
これは、私は道場で相手の方にやられたことがあります。
後は、動かせない位置に駒を打つことですね。
敵陣の一段目に歩や香を打つことそれから敵陣の一、二段目に桂馬を打つことですね。
その他にも、「連続王手の千日手」のような、ちょっと難しい反則も存在するので、興味ある人は調べてみると楽しいでしょう。
まとめ
将棋における反則をまとめてみました。
これらのうち、厳密には、「待った」と「二手指し」を禁じ手と呼ぶかはわかりませんが、とりあえず細かいことは気にしないことにしましょう^^
遊びとして指す将棋では、たまにルールを正式なものと変えてやってみたりするのも面白いです。
例えば「待った」を3回まで許すとか、「二歩」や「打ち歩詰め」をありにしてみるとか。
他にも色々工夫してスリルのあるルールにすることができます。
条件がそろうと駒がワープできるようにするルールとかも面白そうですね^^
今回はここまでです。
そのうち機会があれば、二歩が何故反則であるのかとかについても、書いていきたいです。